-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
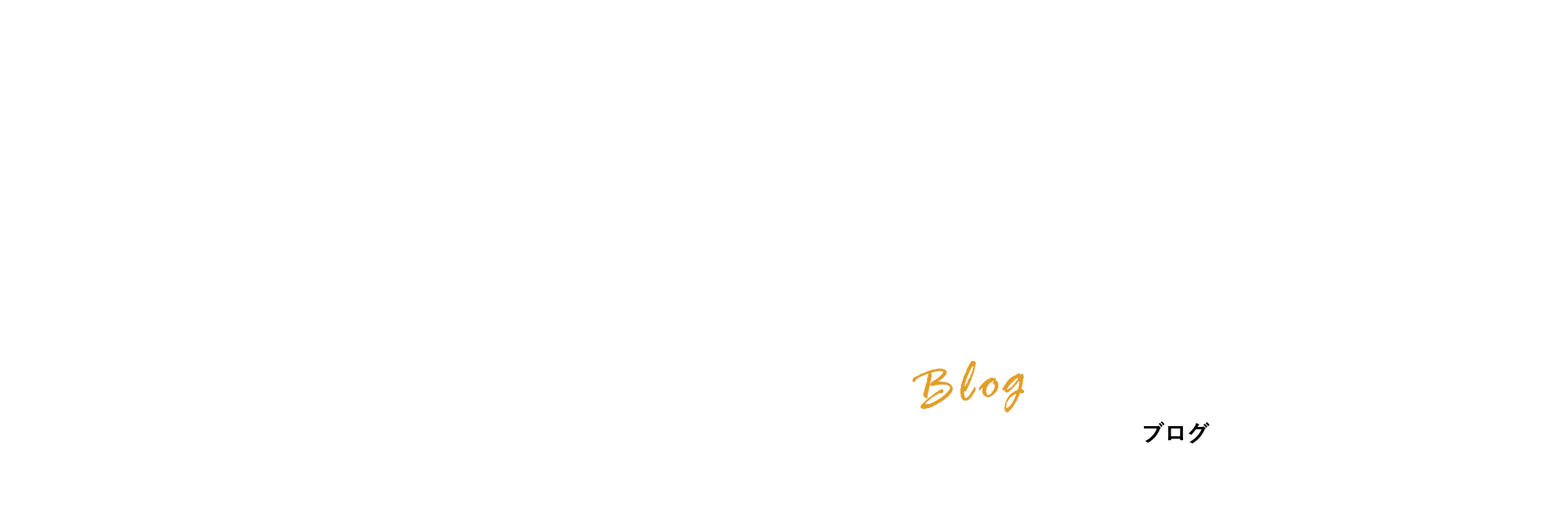
皆さんこんにちは!
林運送サービス、更新担当の中西です。
さて今回は
~確認事項~
ということで、今回は、配送業務において重要な7つの確認事項を深く解説します。
配送という仕事は、一見「荷物を運ぶだけ」のように見えて、その裏側には多くの確認・判断・対応の連続があります。
実際、配送クレームの多くは「確認不足」が原因。
そのため、現場で“当たり前”と思われがちな確認作業を、いかに確実に行うかが品質・効率・安全のすべてを左右します。
伝票と実物の照合(個数・サイズ・荷姿)
壊れやすい荷物/温度管理が必要な商品(精密機器、生鮮品など)の確認
着時間指定・置き配指示の有無
📌 「積み忘れ」「違う荷物を積んだ」は最も多いトラブル原因。Wチェック体制が理想。
最短ルート or 優先納品順(納品時間指定・交通状況を考慮)
渋滞・通行止め情報、天候予測の確認
高さ制限・車両進入禁止区域の事前チェック
🗺️ 無駄な走行や納品遅延を防ぐには、出発前のルート確認が命です。
タイヤの空気圧/オイル・水/ライト・ブレーキの確認
荷崩れ防止のためのラッシング・固定具の使用
配送端末やスマホ、電池残量のチェック
🔧 車両トラブル=納品遅延に直結。運行管理者との連携も大切です。
時間指定がある場合、5〜10分前に到着連絡を行う(企業納品では特に重要)
荷受人の在宅/担当者の確認
現地の駐車位置や搬入ルートの確認
📞 不在や受け取り拒否のリスクを防ぎ、スムーズな受け渡しが可能になります。
荷物の外装破損/濡れ/荷崩れがないかの最終確認
商品の伝票との照合(バーコード読み取り/手書きサイン対応)
指定場所・方法への納品(置き配・カゴ車入替・棚入れなど)
📦 受け取り側の第一印象は、荷物の状態と応対で決まります。
受領印・サインのもらい忘れ防止(手書き/電子受領)
時間・受け渡し者の記録(誰に渡したかを明確に)
再配達になる場合の対応(理由/次回希望時間の記録)
💡 これがないと「届いていない」「受け取っていない」というクレームの火種になります。
配送件数・未納品件数の報告
クレーム・要望のフィードバック(例:常温品が冷えていた、ドライバー対応が良かったなど)
伝票・納品書・未納荷物の提出/再配達の予定確認
📋 現場の声を次回に活かすことで、サービス品質の改善が可能になります。
配送業務はスピードが求められる反面、焦りや慣れがトラブルの元になります。
だからこそ、「確認することを習慣にする」ための仕組みづくりが重要です。
✅ チェックリストの導入(紙・アプリどちらでも可)
✅ 朝礼での指差し確認訓練(ドライバー意識の統一)
✅ 教育マニュアルの整備(新人〜ベテランまで基準統一)
✅ 再配達・事故の“原因分析会”でチーム改善
📈 「確認したつもり」から、「確認したという証拠」へ意識を変えるのがポイント。
配送の仕事とは、単にモノを届けるだけではありません。
それは「信用」「品質」「企業の顔」を一緒に届ける、大切な役割です。
そしてその信頼は、日々の小さな確認の積み重ねで守られています。
配送前の荷物チェック
ルートと時間の確認
丁寧な受け渡し対応
報告とフィードバック
このすべてを大切にすることが、「また頼みたい」と思われる配送業者への道です。
※営業目的でのお電話・お問い合わせは業務遂行の妨げとなるためお控えください。

皆さんこんにちは!
林運送サービス、更新担当の中西です。
さて今回は
~再配達管理~
ということで、今回は、再配達が引き起こす問題とその実態、そして配送業者・荷主・消費者が一体となって再配達をどう管理・削減していけるのか?について深く解説していきます。
いま配送業界では、「人手不足」「燃料高騰」「荷物増加」という三重苦の中、“再配達”という見えないコストが大きな課題となっています。
再配達とは、最初の配送時に不在だった荷物を、改めてもう一度届け直すことです。
一見、単なるサービスの一環のように思えますが、物流の現場にとっては大きな負担です。
都市部での再配達率:約12〜15%
地方部での平均:約8〜10%
EC購入層(20代〜40代)の高い再配達傾向
つまり、10件に1〜2件は再配達という現実があります。
労働負荷の増加
→ 1件の再配達で10〜15分のロス。年間数百時間に相当。
燃料・車両コストの増加
→ CO₂排出増加にもつながり、環境負荷も高い。
業務効率の低下
→ 他の荷物の配送遅延や、次のエリアへの遅れ。
人手不足の悪化に拍車
→ ただでさえ厳しい人材確保がさらに難しく。
📦 「無料サービス」では済まされない、“物流コストの無視できない要因”となっています。
日中在宅率の低下(共働き世帯の増加)
若年層の再配達依存傾向(時間指定せず注文)
細かな時間指定に対応できない体制
ドライバーが個別連絡できない
曜日指定などのオプションが有料
荷主・ECサイトとの連携が不十分(置き配指示やスマホ通知の漏れ)
不在票の確認ミスや紛失
マンションや戸建てでの宅配ボックス設置率向上がカギ
利用者に「置き配」の意識づけを行う
ドライバーにも置き配ガイドラインの徹底
📦 EC大手では初期設定を「置き配推奨」に切り替える動きも。
配送予定日時の前日通知・直前通知
不在時はLINEやSMSで再配達手続きリンクを即送信
チャットボットによる再配達受付も可能
📲 デジタル化によって、人手をかけず再配達率を低下させることができます。
配送管理システム(TMS)にて、再配達件数・再配達時間を自動記録
月別・エリア別に分析 → 対策の重点化
📊 「見える化」することで、教育・体制整備・荷主へのフィードバックが可能に。
EC事業者に対し、「再配達を前提としない配送設計」の提案
購入時点での時間指定義務化・住所不備防止
大口荷主とは共同プロジェクト化する例も増加中
📦 荷主とのパートナーシップが、根本的改善のカギです。
再配達対応時の「丁寧な説明」と「対応スピード」
置き配不可時の正確な不在票記入
スマートフォン操作・顧客応対のマナー研修
👨🔧 ドライバーが“サービスマン”として評価される時代へ。
再配達の問題は、物流業者だけの努力では解決できない社会課題です。
そこで、今後必要とされるのは次のような「三者連携」です
| 主体 | 役割 |
|---|---|
| 配送業者 | 再配達を前提としない体制の構築・データ管理 |
| 荷主(EC・小売) | 配送選択肢の提供・住所/日時入力の義務化 |
| 消費者 | 置き配・ボックス利用・通知確認の協力 |
また、政府や自治体も、環境負荷削減や交通混雑対策の一環として宅配施策を支援し始めています。
再配達は“仕方がないもの”ではありません。
むしろ、業務の効率化・環境対応・顧客満足の向上を同時に実現できる「改善のチャンス」でもあります。
アナログからデジタルへ
孤立した対応から連携型の仕組みへ
消費者との共創型サービスへ
物流の未来を見据えるなら、再配達対策は今すぐ始めるべき「最優先課題」です。
※営業目的でのお電話・お問い合わせは業務遂行の妨げとなるためお控えください。
